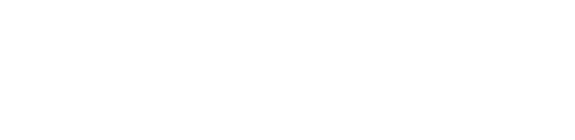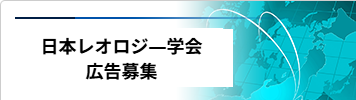日本レオロジー学会の概要
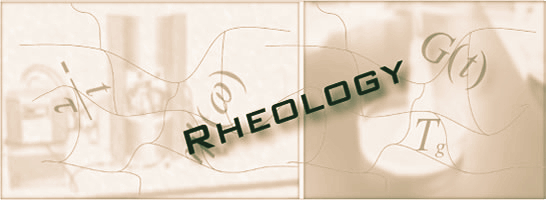
レオロジー(Rheology)とは、物質の流動と変形を取り扱う近代科学の一分野です。対象とする物質は問わず、弾性論、塑性論、流体力学等で取り扱うには複雑すぎる物質や、現象が研究対象になります。レオロジーの目的は、物質の複雑な力学挙動を分子論的、構造論的に解明すること、及びそれらの成果を工業に応用し技術の革新や、製品の性能の向上に役立てることです。工業材料のレオロジー挙動が、実際の作業工程において重要な役割を演じることは多く、プラスチック、繊維、ゴム、パルプ、油脂、接着剤、セラミック、薬品、金属材料など、レオロジーが関与する工業分野は広がっております。最近では、自動車、電気、航空機工業などの材料のユーザーや、石油、石炭の採掘関係などにおいても、レオロジーの役割が大きく重要になってきています。
第27期日本レオロジー学会会長挨拶 令和7年(2025年)5月 ~ 令和9年(2027年)5月

一般社団法人日本レオロジー学会 第 27期 会長
鈴木 洋(すずき ひろし ) 神戸大学
令和 7年(2025 年) 5 月 ~ 令和 9年(2027年)5月
この度、一般社団法人日本レオロジー学会第27期会長を拝命いたしました。非力ではありますが、会員の皆様のご支援のもと、学会の発展に寄与させていただければと存じます。どうぞご協力お願い致します。
さて、会員の皆様は「レオロジー」についてよくご存じかと思いますが、一般に「レオロジー」という言葉は普及していないかと存じます。カタカナで表記しており、また大学でも講義されるところは少なく、意味がわからないということかと思います。さらに教科書を見ても、学会の予稿集を見ても、複雑な議論が多く、「レオロジー」という名称だけではなく、複雑で理解できないものと考えられている方も多いのではないかと拝察します。しかしながら本サイトの概要にもありますように、様々な工業製品がレオロジーの知見を基に生み出されており、幅広い応用分野において、重要な役割を果たしております。
「レオロジー」という言葉は、流れを意味するギリシャ語の「レオス」と学問を意味する「ロジー」を組み合わせて生まれた言葉です。そのまま日本語にすると、「流れ学」となってしまい、ベルヌーイらが構築した「流体力学」と区別できないので、「レオロジー」とそのままカタカナで表記しております。レオロジーは固体力学や流体力学と異なり、固体・液体の複雑な挙動を取り扱う科学です。複雑系科学の一種であり、上記古典的な学問とは一線を画します。一言でいうと構造変形学でしょうか?レオメータの使い方を研究しているように思われている方も少なくないと思いますが、実際は複雑な構造を有する固体や、かつて非ニュートン流体と呼ばれた複雑流体の挙動を取り扱い、その複雑な挙動の原因を解明して、様々な物質・流体を取り扱う応用技術を開拓することを目指しています。少し古典的な学問から一歩進んだ議論になるので、難しいという側面は確かにありますが、極めれば新しい物質や新たな機能性流体を生み出すことが可能となると思います。
まずは本学会で主催している「レオロジー講座・基礎編」を受講していただいて、さらに「レオロジー講座」「レオロジーイブニングセミナー」「食品のレオロジー」に参加していただき、春の「レオロジー学会年会」、秋の「レオロジー討論会」にご興味を持っていただければと存じます。その他、国際学会・国際活動も積極的に推進しておりますので、皆様のご参加を心より歓迎いたします。
末筆ながら、小職をご推挙いただきました諸先輩方に深く感謝し、皆様のご健勝を心よりお祈りいたします。今後とも日本レオロジー学会のために、鋭意努力させていただきますので、ご指導のほどよろしくお願い致します。
第27期役員
一般社団法人日本レオロジー学会 第27期役員名簿
任期: 令和7年(2025 年) 5 月 ~ 令和9年(2027 年) 5 月
| 役職 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 会長 | 鈴木 洋 | 神戸大学 |
| 副会長 | 浦山 健治 | 京都大学 |
| 副会長 | 髙橋 勉 | 長岡技術科学大学 |
| 副会長 | 増渕 雄一 | 名古屋大学 |
| 理事 | 新井 武彦 | 英弘精機株式会社 |
| 理事 | 井賀 充香 | 日本ペイントコーポレートソリューションズ株式会社 |
| 理事 | 猪股 克弘 | 名古屋工業大学 |
| 理事 | 浦川 理 | 大阪大学 |
| 理事 | 酒井 崇匡 | 東京大学 |
| 理事 | スクマラン サティシュ | 山形大学 |
| 理事 | 田中 敬二 | 九州大学 |
| 理事 | 田村 英子 | 花王株式会社 |
| 理事 | 中村 浩 | 株式会社豊田中央研究所 |
| 理事 | 堀中 順一 | 京都大学 |
| 理事 | 松宮 由実 | 大阪大学 |
| 理事 | 山本 剛宏 | 大阪電気通信大学 |
| 監事 | 井上 正志 | 大阪大学 |
| 監事 | 徳満 勝久 | 滋賀県立大学 |
一般社団法人 日本レオロジー学会会員数(令和7年3月31日)
| 正社員 | 550名 |
|---|---|
| 学生会員 | 44名 |
| 公共会員 | 1件 |
| 賛助会員 | 45事業所46口 |
主な行事・出版物
日本レオロジー学会誌(年5回刊行、全会員に配布)
レオロジー関係の総説、原著論文、解説記事、会告には学会活動のお知らせなどを掲載しています。
年会(毎年6月、2日間)
研究発表のほか、学会賞等受賞講演、同時に年次総会を行います。
レオロジー討論会(毎年10月、3日間)
レオロジー関係では国際的にもよく知られた国内最大の研究集会です。
レオロジー講座(毎年12月、2日間)
レオロジーの基礎と測定法に関する初級講座で、1981年開講以来毎回約100名の受講者があり、工業技術者のレオロジー入門コースとして極めて高い評価を得ています。
講習会等
「レオロジー講座・基礎編」、「食品レオロジー講習会」、「レオロジー・イブニングセミナー」を開催しております。
国際会議
1983年、1984年、1988年、1996年、及び2002年には国際シンポジウム、1991年には日中レオロジー会議、1994年には第1回太平洋レオロジー会議、2010年には第5回太平洋レオロジー会議を主催しました。2016年にはレオロジー国際会議(ICR2016)を主催しました。
お知らせ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
■ 受賞写真
渡辺 宏 元会長が米国レオロジー学会Binghamメダルを受賞しました。
土井 正男 元会長が(2001年Bingham Medalists)Fellowship Awardを受賞しました。