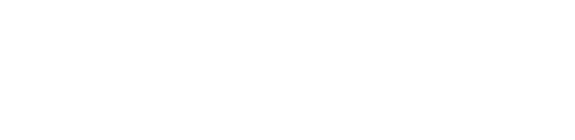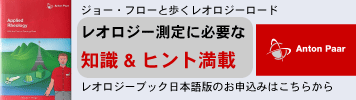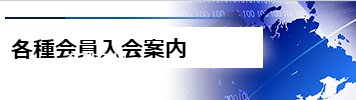最新TOPICS
本部行事 ※緑色のアンダーラインで囲われた箇所をクリックで、各行事の詳細をご覧いただけます。
日時:2024年(令和 6年) 5月 16 日(木)、17日 (金)
会場:名古屋工業大学 御器所キャンパス4号館ホール(〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日時:2024年(令和 6年)7月 4日(木)9:30-17:30
開催方法:オンライン開催 (Zoom利用)
※参加申込は、5/21(火)以降に開始します
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日時:2024年(令和 6年) 10月17日(木)、18日(金)
会場:山形テルサ(〒990-0828 山形県山形市双葉町1‐2‐3)
懇親会:ホテルメトロポリタン山形( )
※講演申込は、5/21(火)以降に開始します
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
■第23回食品レオロジー講習会 ‐初心者のための実習と基礎:食感・風味の制御に向けて-(3/23版)
日時:2024年(令和 6年) 11月 7 日(木)、8日 (金)
会場:東京大学生産技術研究所 An棟3階 An302(〒153-8505 東京都目黒区駒場4-6-1
※参加申込は、5/21(火)以降に開始します
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
■第44回レオロジー講座‐様々なソフトマターのレオロジー-(3/23版)
日時:2024年(令和 6年) 12月 3 日(火)、4日 (水)
開催方法:オンライン開催(Zoom利用)
※参加申込は、5/21(火)以降に開始します
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
支部行事・研究会行事 ※緑色のアンダーラインで囲われた箇所をクリックで、各行事の詳細をご覧いただけます。
日時:2024年(令和6年)6月 4日(火)13時30分から16時50分
会場:オンライン開催(Zoom利用)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
個人情報保護規定
日本レオロジー学会著作権規程
■ 日本レオロジー学会著作権規程 ・ Copyright Rules of the Japanese Society of Rheology
本規程は、本会が独立した団体として、他の団体または個人と著作権に関わる交渉ができるようにすることにより、著作者自身を著作権管理に関わる事項から解放、また著作物の周知性の向上などの便益の拡大を図ることができることを目的としています。そのため、本規程では著作物の著作権を本会に譲渡してもらうことを原則としますが、それによって著者ができるだけ不便を被らないよう配慮しています。
インボイス登録番号について
2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日)は課税業者に該当します。適格請求書発行事業者の登録番号は、
「T7130005012293」です。
事務局アクセス・問い合わせ先
〒600-8815
京都市下京区中堂寺粟田町93番地
京都リサーチパーク6号館3階305号室
一般社団法人 日本レオロジー学会
TEL:075-315-8687 FAX:075-315-8688
https://www.srj.or.jp
※●を@にかえてください
member●srj.or.jp(庶務)
office●srj.or.jp(講習会申込)
online●srj.or.jp(オンライン行事申込)
journal●srj.or.jp(学会誌)